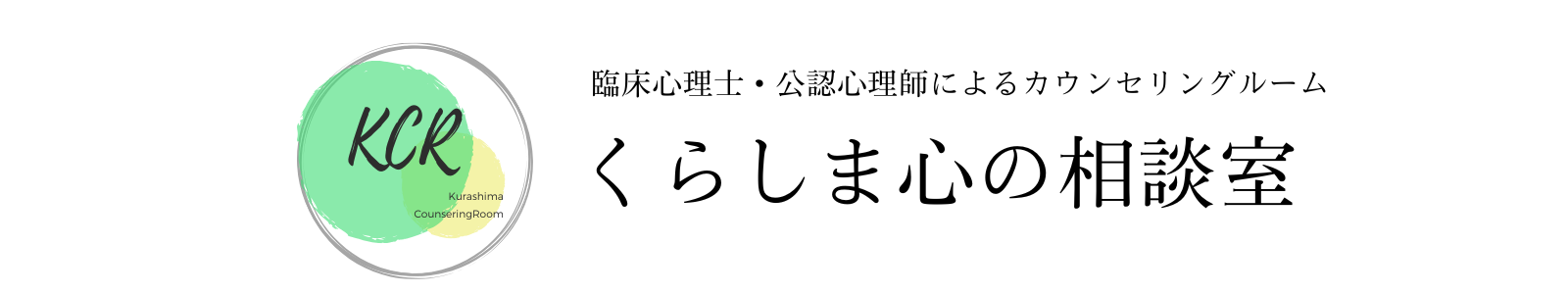このブログでは、里親にも登録している臨床心理士が子どもの心について分かりやすくお伝えしています。
「里親」と聞くと、多くイメージされるのは子どもを養子として迎えるということです。私の場合も、周囲の人へ里子を紹介する際に「養子ってこと?」と皆さん口を揃えておっしゃいました。「養育里親です」というと、「そういった制度があるなんて知らなかった」という意見がほとんどです。日本では、昔から後継のいない家に親戚筋から子供を養子に出す文化があり、そのイメージが広まっている影響だと思います。
この記事ではこんなことがわかります。
里親には、養子縁組里親、養育里親、専門里親、親族里親の4つがある。それぞれ預かる期間や対象が異なる。里親を希望する人は理解した上で、選択することが出来る。
養子縁組里親 (養子縁組を希望する里親)
1つ目は一番世の中に知られている養子縁組里親です。
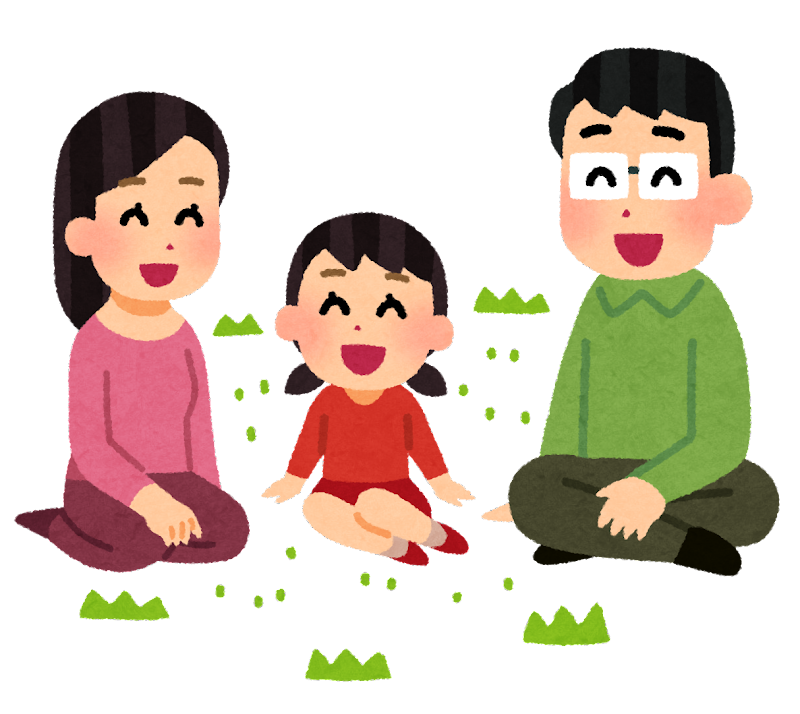
養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁組があります。特別養子縁組とは、実親との親子関係を断ち、育ての親との新しい親子関係を結ぶ制度です。普通養子縁組とは、いわゆる婿養子を想像してみて下さい。実親との親子関係を存続したまま養親と親子関係を作るという二重の親子関係となる制度です。
養子縁組里親とは、基本的には特別養子縁組を希望する里親が、養子縁組の必要な子どもを養育します。養子になることを希望する子どもと、里親との間に数ヶ月の交流期間が設けられます。その後、半年〜1年程度親子として一緒に生活し、養育を行います。その後、養子縁組の法的な手続きとなります。養子縁組里親の期間は縁組が成立するまでです。縁組が成立したら、里親という分類ではなく、養子を受け入れた一家族として生活していくことになります。
我が家は養子縁組里親と養育里親を希望しています。やはり、養子縁組里親は年間を通して希望件数は少ないです。実親としては子どもを手放したくない気持ちが強いのでしょう。
養育里親
2つ目は、養育里親です。
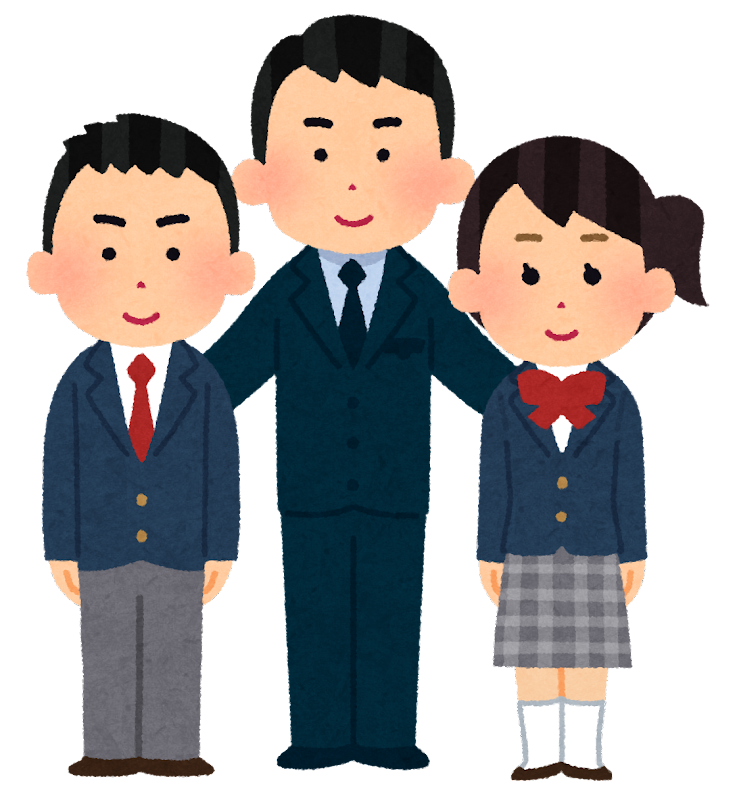
社会的養護が必要な子どもを、一定期間家庭で養育します。養育する期間は、短期~長期とさまざまで、里親の希望が考慮されます。原則、子どもが18歳になるまでの養育ですが、子どもの状況によって大学進学等を理由に延長するケースもあります。
養子縁組里親に比べて希望件数は多いです。子どもを完全に手放したくはないが、一緒に暮らすことは難しい…そういった事情を抱える家庭も数多くあります。
希望する家庭には、児童相談所から年間5〜6件くらい事例提供があるそうです。
専門里親
3つ目は専門里親です。

こちらは耳慣れない方も多いと思います。虐待経験、非行の問題、障害がある等の理由により専門的な援助が必要な子どもを養育する里親を指します。専門里親になるためには、別途要件や研修を受ける必要があります。専門里親の登録有効期間は2年で、更新するには研修を受ける必要があります。専門里親の方は常に研修を受け、子どもの養育に対し研鑽していることがうかがえます。
親族里親
4つ目が親族里親です。
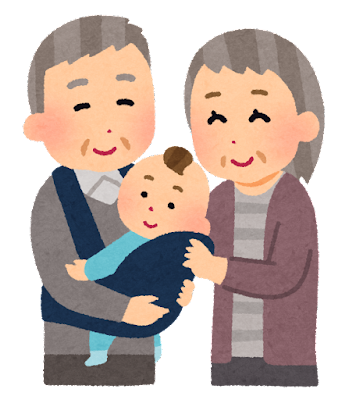
両親や監護する者が死亡、行方不明、拘禁、入院などにより子どもを養育できない場合、祖父母、叔父、叔母などの親族が子どもを養育します。子どもの精神的な負担を考慮し、養育里親よりも親族里親が優先されることもあります。
私が小学生高学年の時にも、同級生の子が「妹が出来た」と言って小学校低学年の子を紹介されたことがありました。「一人っ子だったのにどうして?」と母親に聞くと、彼女の従姉妹にあたる子(同級生の母と従姉妹の母が姉妹)で、母親が急死したことで彼女の家族が引き取ることになったという話でした。実は身近にもあったことを思い出しました。
それなら養子になれば良いのでは?と思われる方もいらっしゃると思います。もちろん、養子になることも可能です。親族里親と養子の大きな違いは、里親の場合、自治体から生活費などの支援があることです。
親族里親の制度は2002年度から始まりました。まだ20年ほどしか経っていないのです。2000年に児童虐待防止法が施行されたので、児童虐待が社会問題となった頃です。子どもと実親との関係が難しい場合、まずは親族に預けられることも多いと思います。しかしそう言った場合、経済的な課題に直面します。祖父母に預けられる場合、リタイヤ後で年金収入のみでは子育てはかなり大変です。そこで里親の制度が導入され、経済的にも社会的にも支援できるようになっています。
里親に対する支援とは?
里親のイメージが少し湧いてきたでしょうか。ここからは、より現実的話題話に入ってきましょう。
まず里親に対する支援として大きいのは、手当が支給されることです。
- 養子縁組里親 一般生活費、教育費(約50,000円〜60,000円)
- 養育里親 里親手当90,000円(2人目以降も同額)
+一般生活費、教育費(約50,000円〜60,000円) - 専門里親 里親手当141,000円(2人目も同額)
+一般生活費、教育費((約50,000円〜60,000円) - 親族里親 一般生活費、教育費(約50,000円〜60,000円)
それに加え、もちろん児童扶養手当の支給もあります。通常、里子の口座に積み立てておき、年度末に児相が確認します。もちろん、必要があれば使っても良いお金ですが、支出管理が必要になります。
里親手当というのは、里親としての活動費であり、里親会への参加や研修会、啓蒙活動への資金となっています。ブログで発信することも、この活動に該当するのかもと思っています。
これらの金額を多いと思うか、少ないと思うかは、人それぞれかと思います。しかし、子ども1人育てるというのは、本当にお金が要るものです。
手当だけではなく、困ったことは里親会や、先輩里親さんに相談したり、児童相談所の職員へ適宜相談することもできます。中でも、信頼できる先輩里親さんと関係を持っておくことが大切だと思います。児童相談所は県の管轄で、どうしても年度で担当者が変わってしまい、なかなか継続的には難しいと感じています。その点長年里親をされている先輩にお話したり、経験談を聞くことで、色々と気付かされる部分が多いと思います。
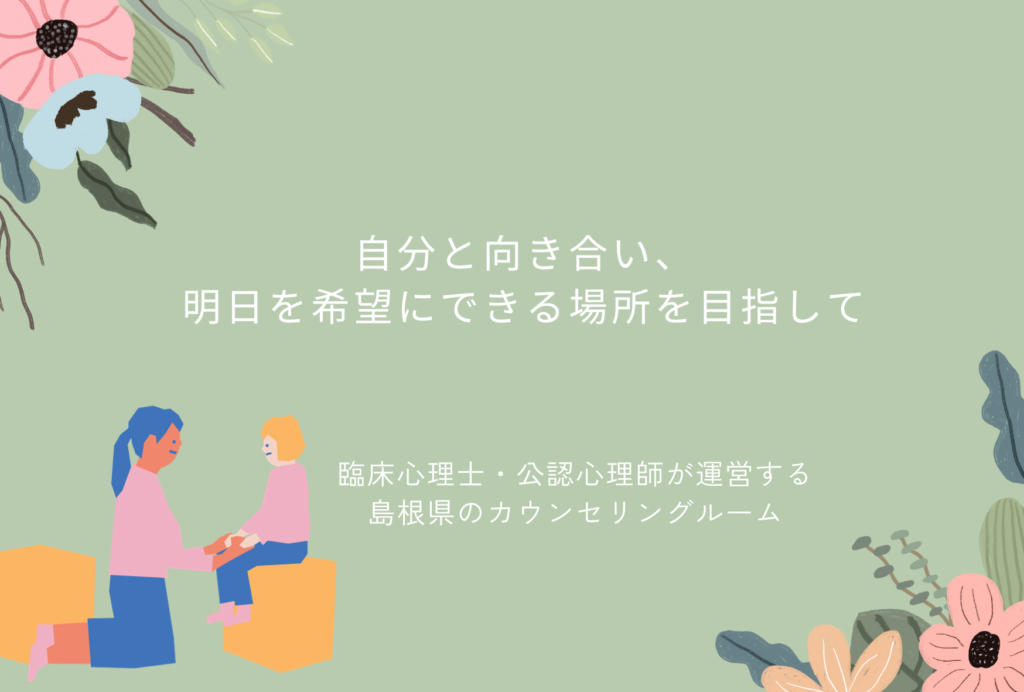
くらしま心の相談室では、里親のことから、子育てのお悩みまで、幅広く対応しております。お気軽にご相談ください。
公式LINEにて無料カウンセリングを実施中!