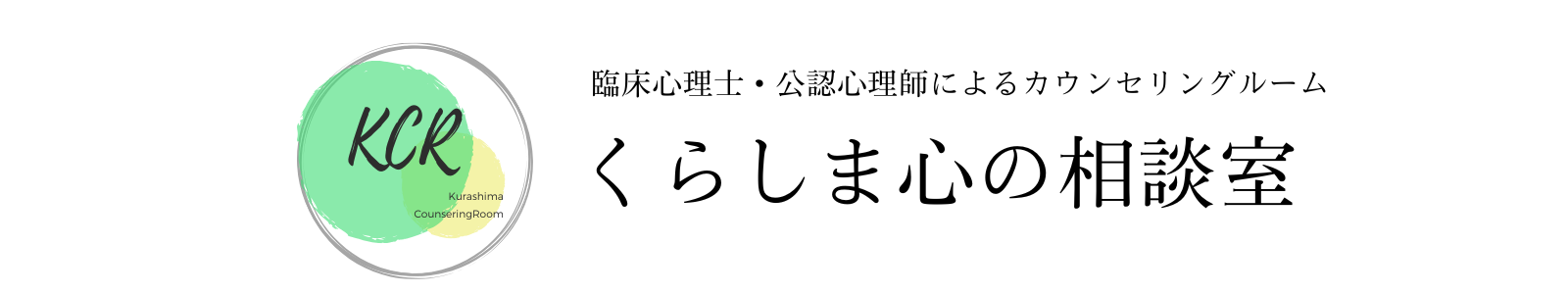アルコール、薬物、買い物、DVなど、「〜依存症」と聞くと、とても恐ろしい病気だと感じられる方が多いと思います。”依存”することは、悪い側面だけでなく、良い側面もあります。
この記事はこういう方に向いています
- このままだと依存症になってしまうのではないかと不安になっている
- 家族や周りの人が依存症なのではと心配している
- どこまでが普通で、どこからが依存症なのか知りたい
依存には「良い依存」と「悪い依存」がある

まずは依存についてです。「依存」とは、何かに頼って存在したり、生活したりすることです。「依存」だけでは、特に悪い意味ではありません。
しかし、依存の中には「良い依存」と「悪い依存」があります。
「良い依存」とは、主体性をもち、相手を尊重しながら、お互いに支え合い、助け合う関係です。そして、相手や物と程よい距離を取ることできます。
反対に「悪い依存」とは、自分が安心や満足を得られないために、相手や物にしがみついたり、支配したり、束縛しようとする関係です。そして、悪い依存が進むことで、依存症になると言われています。依存症になると、相手や物に愛情や助けを求め過ぎてしまい、それがなくては生活できない、生きていけない状態に陥ってしまいます。
依存症は、物質依存、行為依存、人間関係依存の3つのタイプ

依存症には大きく分けて3つのタイプがあります。
1.物質依存《アルコール、タバコ、薬物、カフィエインなど》
ある物質を摂取することで、快楽や刺激を感じ、その物質に執着してしまう状態です。
2.行為依存《ギャンブル、買い物、ネット、ゲームなど》
ある行為をする過程で興奮したり刺激を感じ、その行為自体に執着してしまう状態です。
3.人間関係依存《ストーカー、DV、いじめ(一部)など》
ある特定の人との人間関係に依存し、人との繋がりを強く求めようとします。そして歪んだ人間関係に執着してしまう状態です。
物質依存の多くはアルコール依存

アルコール依存症は全国で約80万人以上とも言われています。100人中6〜7人、30人中2人くらいの割合になります。会社や組織規模で考えても、数人は存在する計算になり、身近な病気と言えます。
さらに、アルコール依存症予備軍は約約440万人と言われ、3人に1人は将来的にアルコール依存症になってしまう可能性があるという研究も出ています。
2008年頃から、ストロング系チューハイが販売されたことにより、多量せずともアルコールの過剰摂取となり、依存症リスクへ懸念されてきました。
2024年1月アサヒビールとサッポロビールは、健康へのリスクを考慮し、ストロング系チューハイを販売縮小すると発表しました。
:quality(50)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/EOVQFYAVHRLEPJGPPCLOENG5BI.jpg)
依存症の観点からしても、ストロング系のお酒は非常に危険性が高いため、付き合い方には注意が必要です。
アルコール依存症は主に精神科、心療内科で治療することが望ましいです。
物質依存で次に多いのが、タバコ(ニコチン依存)と言われています。2006年より、禁煙外来が保険適用されたことや、2018年に望まない受動喫煙を防止するために、法改正が行われ、2020年には原則施設屋内では全面禁煙が義務付けられました。そうした流れから、喫煙者は近年減少傾向にあります。
島根県内でも禁煙外来を設けている医療機関も数多くあります。リンクをご参照ください。
若者の間では、エナジードリンクや、市販薬への依存が問題視されています。エナジードリンクにはカフェインが含まれており、カフェインには依存性があります。コーヒーにもカフェインが含まれていますが、コーヒーのカフェインは1杯辺り約70mg程度です。一方、エナジードリンクで多いものとしては、モンスターは約140mgのカフェインが含まれています。
市販薬=薬物です。依存性のある物質が高濃度含まれている場合もあります。安易に過剰摂取することは身体的にも精神的にも危険です。
依存症の多くが、初めは少量で満足出来ていても、次第に少しずつ増量していきます。まずは習慣化させないことが大切です。
行為依存で多いのはギャンブル

パチンコ、競馬、競艇などギャンブル依存症に陥っている人は、全国で約70万人とも言われています。アルコール依存症と同じくらい多い依存症です。
競馬依存に関してはこちらのサイトで防止策について書いていますのでご参照ください。
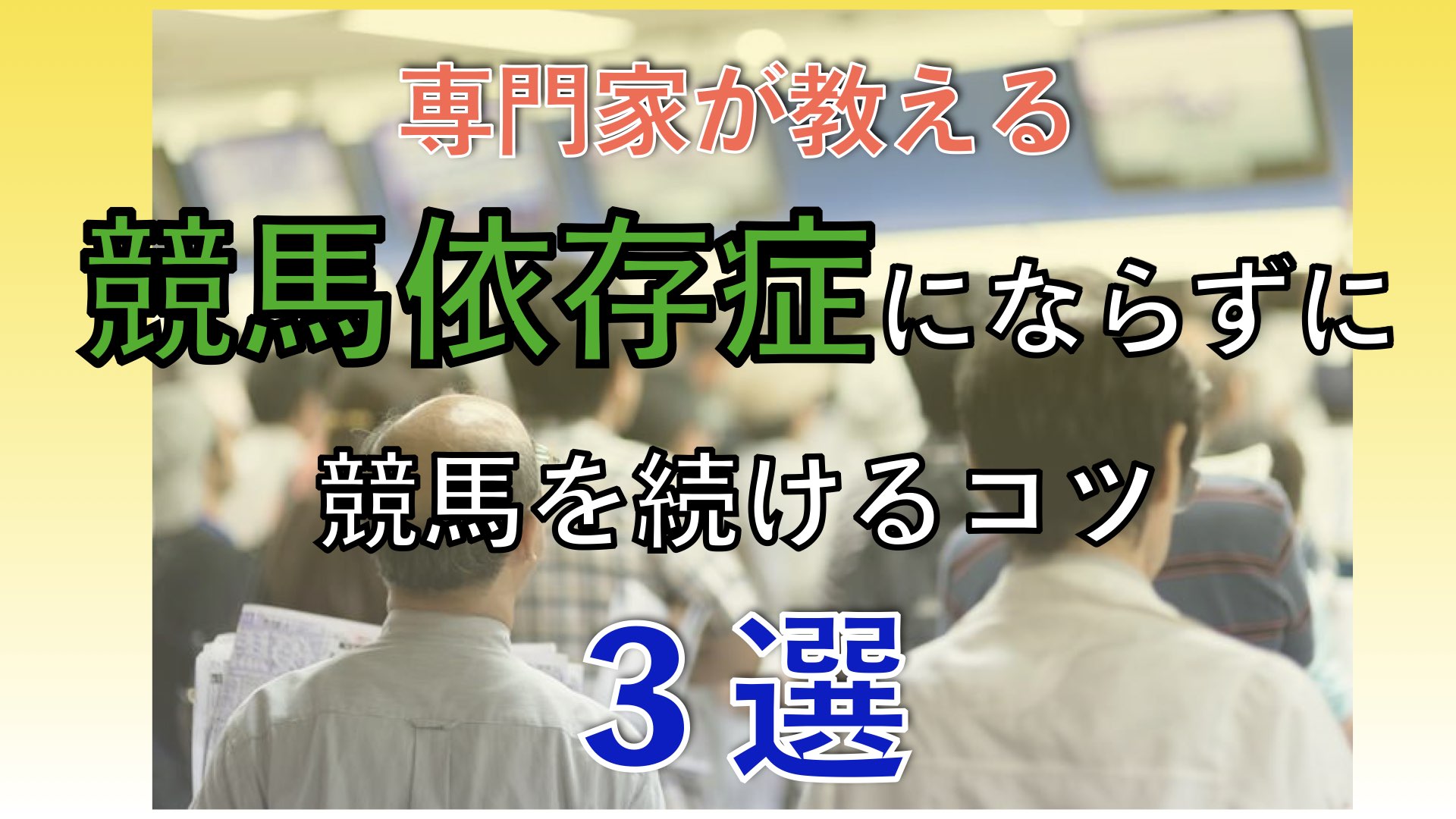
近年、若年層にはスマホ依存も増えています。また、不登校児童の中にはネット依存、ゲーム依存で日常生活が破綻してしまうケースも多いです。
スマホもネットもゲームも、誰しもが日常的に触れるものです。知らず知らずのうちに、慢性化し、抜け出せなくなってしまう、そこが怖いところです。
2021年のベストセラーとなった『スマホ脳』についてはこちらの記事をご覧ください。
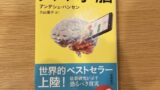
人間関係依存は被害者に注意する
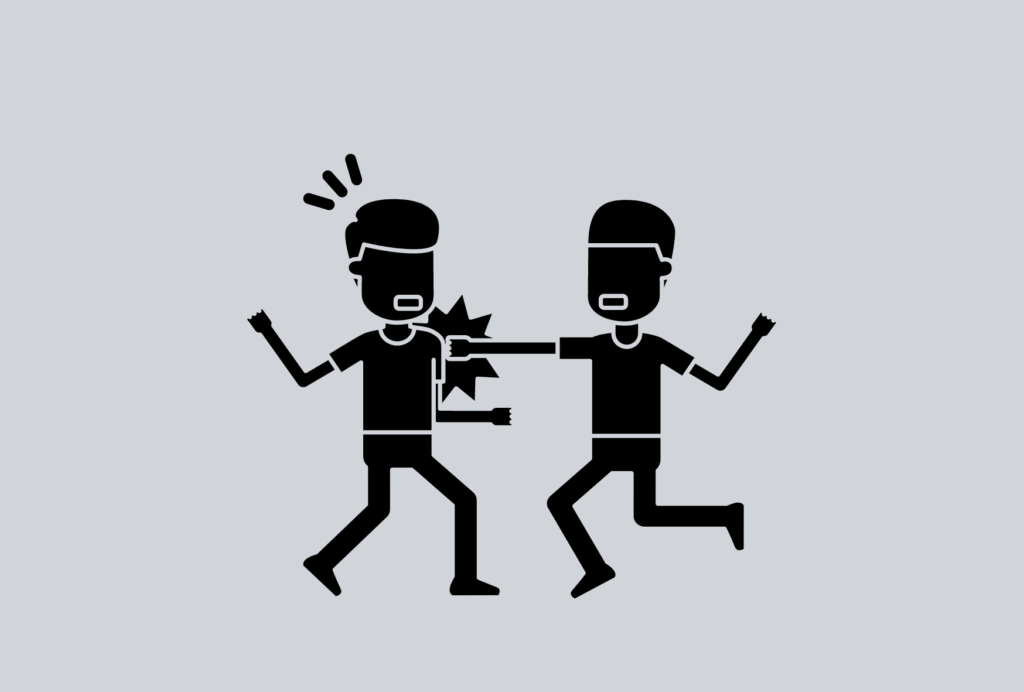
「自分は依存症とは無関係だ」と思っている方にも、注意してもらいたいのが、人間関係依存です。これは、自分自身が依存症にならなくても、相手や周りが依存症になることで、自分自身がその被害者になってしまう可能性があるからです。
例えば、DV(ドメスティックバイオレンス)ではパートナーや家族など親密な関係の中で、身体的・精神的・性的暴力が行われます。DVの心理では、相手を支配したい、思うがままにしたいという気持ちから、力で相手を抑え込む性質があります。加害者の多くが歪んだ心理になってしまい、身体の危険も含みます。そのため、被害に遭わないよう毅然とした態度で臨んだり、被害に遭った際には勇気を出して各所に相談に行くことが必要です。
いじめの一部でも、支配する側とされる側による関係依存があると言われています。加害側にも依存の問題はありますが、いじめ自体は許されるべき行為ではありません。心配があれば、すぐに学校に相談することをお勧めします。
依存症の4つのポイント

依存症の診断はインターネットサイト、診断基準でも示されていますが、押さえるべきポイントを4つお伝えします。
- コントロールできない
一度スイッチが入るとずっとやり続け、途中でやめたり、ほどほどに済ますことができない。自分以外に、周りにも迷惑をかけている。 - 常習的である
どんなに努力や我慢をしても、やめ続けることが出来ない。自分の意志では止めることが出来ない。 - 嘘をつく、否認する
周りから依存症を心配された際、「そんなことない」「やってない」などと否定したり、嘘をついたりしてしまう。相手が傷ついていても「相手のためだ」と言い張ってしまう。 - 離脱症状がある
それをしていないと、イライラしたり、落ち着かない、気分が落ち込むなどの精神症状や、発汗、不眠、頭痛などの身体症状がある。
4つ全て当てはまるなら、依存症が進行している可能性が高く、医療機関への受診、相談することが大切です。全てではないが、いくつか当てはまるのであれば、依存症になる可能性が高いです。医療機関に抵抗があれば、地域の保健所でも相談にのってくれます。

依存症は慢性疾患です。慢性、なので完全に治る病気ではありません。依存症が良くなっていくことを「回復」と呼び、治療には長い年月がかかります。そのため、未然に防ぐことが非常に重要です。
くらしま心の相談室では依存症のお悩みも相談頂けます
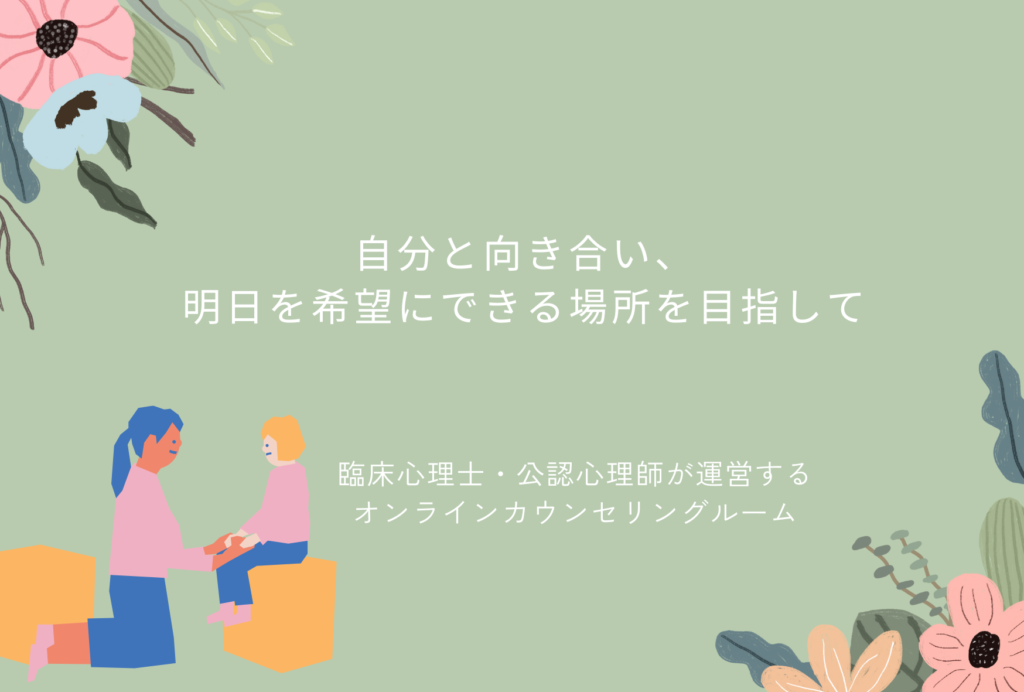
くらしま心の相談室では、医療機関で依存症の患者さんへのカウンセリング経験のあるカウンセラーがお悩みをお聞きします。医療機関には抵抗があるという方、ご家族の依存症にお悩みの方の相談もお聞きします。
話してみることで、少し肩の荷を下ろせることもあります。お気軽にご相談ください。
公式LINEにて無料カウンセリングを実施中!