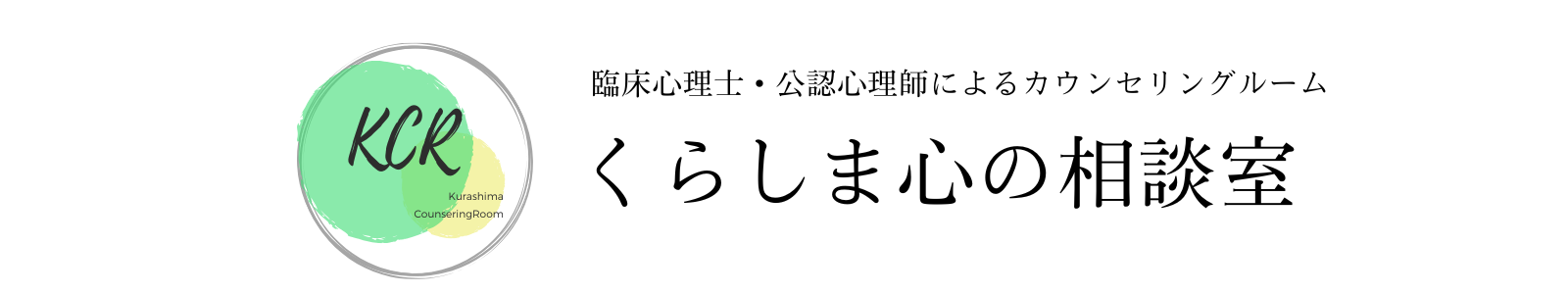心理カウンセラーのKuraです。今まで多くの不登校の子供たち、その親御さんと面接をしてきました。「学校を休みたい」と言う要求に対して、親や先生など大人の気持ちとして、以下の3つが多く聞かれました。
- 「学校に行くのは当たり前」
- 「社会に出たときにもっと大変な思いをするのは自分自身」
- 「休むことで逃げ癖がつくのではないか?」
不登校や、行きしぶりのある子どもを持つ親からよく聞かれるコメントです。こちらについて心理士としての見解をお話しします。
・「学校に行くのは当たり前」→当たり前の基準を見直す。
・「社会に出たときにもっと大変な思いをするのは自分自身」→もう既に大変な思いをしている。
・「休むことで逃げ癖がつくのではないか?」→癖になっているか確認する。
こちらのブログを3分で知りたい方はYouTube動画がおすすめです。
ショート動画では15秒で解説しています。
「学校に行くのは当たり前」の基準は?

「学校に行くのは当たり前」と親が言うことに対して、子供から多く「どうして学校に行かないといけないのか?」と言う質問が出てきます。この質問に対して、きちんと答えを示せる大人はどのくらいいますか?
・勉強のため
・対人関係を学ぶため
・経験を積むため
・習慣を身につけるため など
私もこの質問に、「これです!」と言える答えは見つかっていません(カウンセリングの場合、明確な答えを言う必要はありませんが)。色々と候補は出てきますが、他の場所で勉強できたり、友達と遊んだり、経験を積んだり、家庭で習慣を身につけることも不可能ではありません。学校に限定する明確な理由ではないのです。私が今まで会った不登校の子供たちは、学校に行けない時期もありましたが、大学や専門学校に進学したり、自動車免許をとってアルバイトをしたり、専門家になって仕事をしている人もいます。
「学校に行くのは当たり前」と思う心理は、『自分や自分の周りでは聞いたことがない』という経験則からくる部分も多いです。私は不登校の子と多く接してきたため、もはや学校行くことが当たり前とは思わないです。自分は何を基準、誰を基準に当たり前と思っているのでしょうか。そして今、何を基準に考えるべきなのでしょうか。”当たり前”と思うことに関しても、今一度考えてみる価値はあると思います。
子育ての中では、「こうしたらこうなるのが当たり前」が通用しないのは、経験上ご理解頂けるのではないでしょうか。子育てしながら、親自身も価値観や考え方が変わることも多いです。
「社会に出た時に大変な思いをするのは自分自身」はその通り

「社会に出た時に大変な思いをするのは自分自身」おっしゃる通り、その通りだと思います。そうです、子供自身大変な道を歩んでいるのです。
「何も気に留めず学校に行けるなら、そんな楽なことはない」子供自身そう思っています。学校を休むことで、自分の自信はなくなるし、親にも心配かけるし、先生や友達だってどう思うかわからないし…こんな大変なことはありません。大変な思いは既にしていますし、これから先も、社会に出た時にもしていく可能性はあります。学校に行かないことは、学校のことを考えないことだと思われがちですが、学校に毎日行く子よりも、むしろ不登校の子の方が学校に対して多くのことを考えています。学校に毎日行く子は、それを日常としているので、「なんで学校に行くのか?」と考えることは少ないです。不登校の子は休んでいるにも関わらず、「学校に行かないといけない」とか「学校に行きたくない」など学校のことを考えることが多いのです。
不登校の子たちにとって、学校に行くことは何かしらの苦手さを含んでいます。皆さんも苦手なことを想像してみてください。私は「大勢の人の前で話すことが苦手」です。もし、毎日人前で話せと言われたら、嫌になって休んだりするかもしれません。大人になれば、苦手なことは避けたり、うまい対処法をいくつか身につけていたりします。子供はそんなこと出来ません。苦手なことを考えたり、向き合ったりするのって、すごくエネルギーを使いますし、疲れます。さらに、”学校”という子供の生活に大きく関わる事柄に対して、苦手さをもっているので、そのことと向き合い続けないといけない辛さもあると思うのです。
「休むことで逃げ癖がつくのではないか?」癖になっているか確認
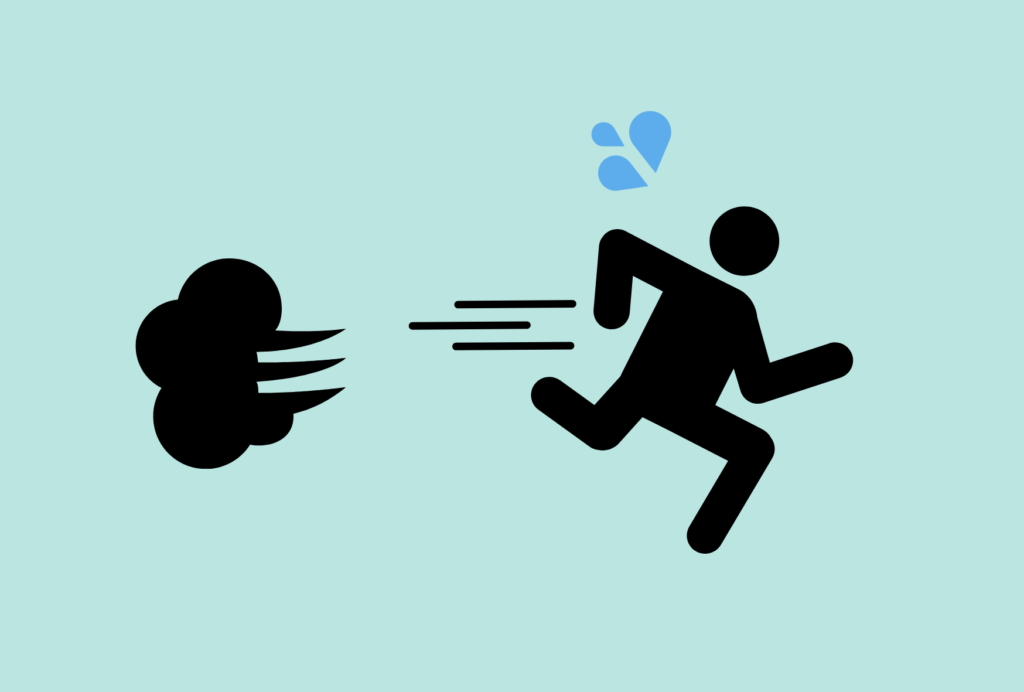
「逃げ癖」言う言葉があります。心理学でいうと、癖とはある程度長い時間をかけて習慣化してしまう現象のことを指します。学校を休むこと以外でも、”自分の都合が悪くなる誤魔化して逃げる”とか、”友達とケンカすると仲良くするのをやめる”など、他の行動においても、”逃げる”という選択が一番に来ているようであれば、逃げ癖と呼べるかも知れません。癖というのは、あまり考えることもせず、その選択をしてしまうことです。爪を噛む癖や、髪を触る癖など、ほとんど無意識に行っていることが多いです。
反対に、”うまく行かなくても、工夫して頑張れることがある”とか、”友達とケンカした時も仲直りできた”、と言ったことがあるのであれば、逃げ癖とは呼べません。その場合は、考えた上で結論として学校行かない選択をしていることになります。とはいえ、子どもの「考える」なので不十分な場合も多く、短絡的に考えていることもありますが、癖ではないことはご理解頂けると思います。
逃げ癖であれば、学校に行くこと以外の逃げ癖に対しても、アプローチしていく必要があります。出来そうなこと、本人のやる気があることからで良いので、挑戦し、諦めず最後まで出来る経験を積み、大いに褒めて自尊心を高めていきます。これが自己効力感にもつながり、「自分もやればできる」気持ちに繋げていけます。
逃げ癖ではなかった場合、学校に行かない一件だけで逃げ癖になる可能性は低いと考えます。もし、学校に行かない以外のことで、逃げるような行動が見られた際は、簡単に逃げる選択を取らないよう関わることで、癖にならないよう防止することも出来ます。今後、逃げ癖にならないよう、防ぐことが出来るのです。
まとめ

子どもが休みたいと言った時の対応についてはこちらのブログでまとめています。
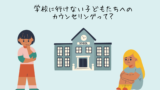
一番身近で見ている親は本当に心配の多いことでしょう。「こんな時、どうしたら良いですか?」と切羽詰まった質問を多く頂きます。その時に大切にして欲しいのは、「親としてさせたいこと」と「子どもがしたいこと」これをきちんと分けて考えることです。”親として登校させたい”これをメインとするなら、そうなさるのも否定はしません。それでうまく行かなくなったとしても、それは親がしたいことであったからで、子ども自身の問題ではないと思います。私がしてきたカウンセリングでは「子どものしたいこと」がメインです。「教室は嫌だけど、保健室なら行きたい」とか、「勉強は嫌だけど、お話しなら良い」とか、少しでもやりたいことが出てくるのであれば、希望は多いにあります。何しろ、苦手なことにチャレンジしている子供達です。やりたいことを支え、出来たことを褒めて、少しずつステップアップすることで自信をつけていくことも可能です。
子どもを支える親自身も心と体の健康を保っておくこと、これも非常に大切なことです。学校に行った行かないで一喜一憂する日々は本当に疲弊します。親自身も誰かに相談したり、気晴らししたりして、乗り越えて行くことが大切です。
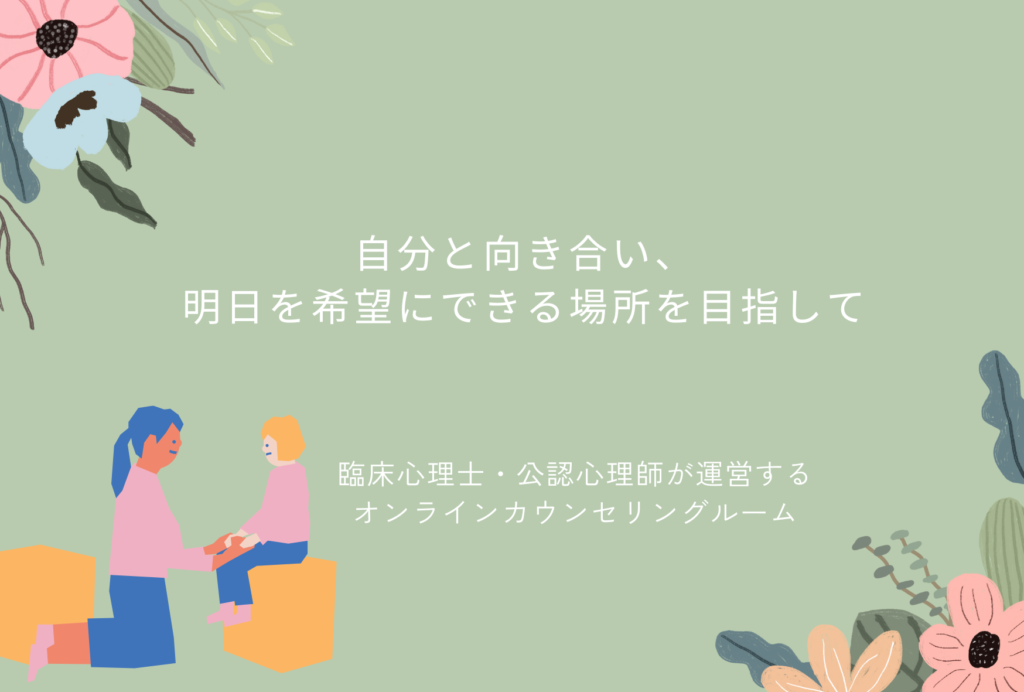
くらしま心の相談室では、子どもの不登校のご相談、親の相談、子ども自身の相談にも対応しております。お気軽にお問い合わせください。
子どもたちのカウンセリングについてはこちらのブログをご参照ください。
公式LINEにて無料カウンセリングを実施中!