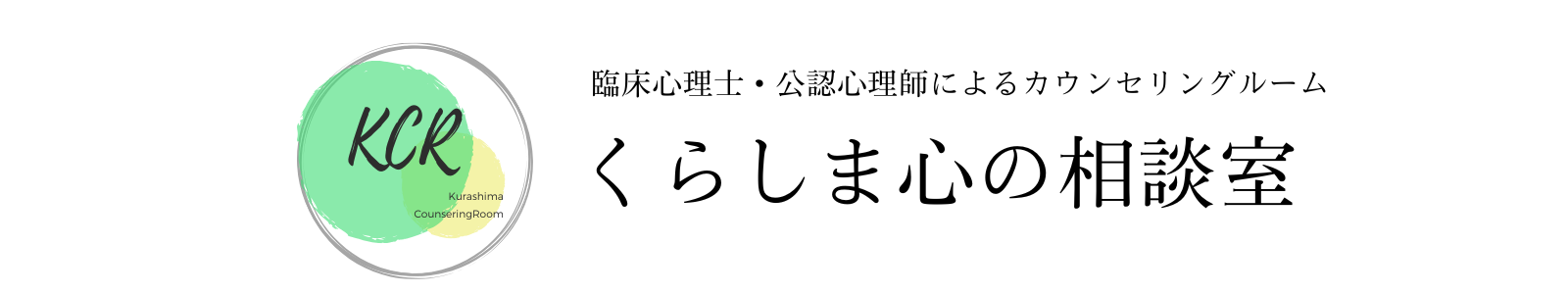このブログでは、里親に関して臨床心理士が分かりやすくお伝えしています。
「里親」と聞くと、保護犬や保護猫を育てること?と先ず思いつく方も多いでしょう。確かにYahoo!検索では初めに「里親、犬」と上位表示されますし、「里親募集」のサイトが先に目に留まります。それくらい犬猫の里親の話題は多いです。しかし、実は「里親」という言葉自体は元々は子どもたちのために70年以上も前から使われてきた言葉だそうです。我が家は犬の里親でもあり、子どもの里親でもある、ダブル里親ですが、今回は子どもの里親についてお伝えします。
*この記事はこんな人に向いています*
「子どもはいないけど、子育てをしてみたい。」
「子育て一段落したけど、もっと子どもを育ててみたい。」
「子育てをして社会に貢献してみたい。」
「子どもが好きで、関わる機会が欲しい。」
少しでもこんな気持ちがある方は、是非最後まで読んでみてください。
里親って何?
里親とは、様々な事情で育てられない親の代わりに一時的に家庭内で子どもを預かって養育する制度で、里親と子どもに法的な親子関係はなく、実親が親権者となります。 里親の期間は短い場合数週間、長い場合は10年以上のケースもあります。季節・週末里親という場合もあり、夏休みだけ、または週末だけ家庭に受け入れることもあります。
具体例のお話(仮定)で見てみましょう。
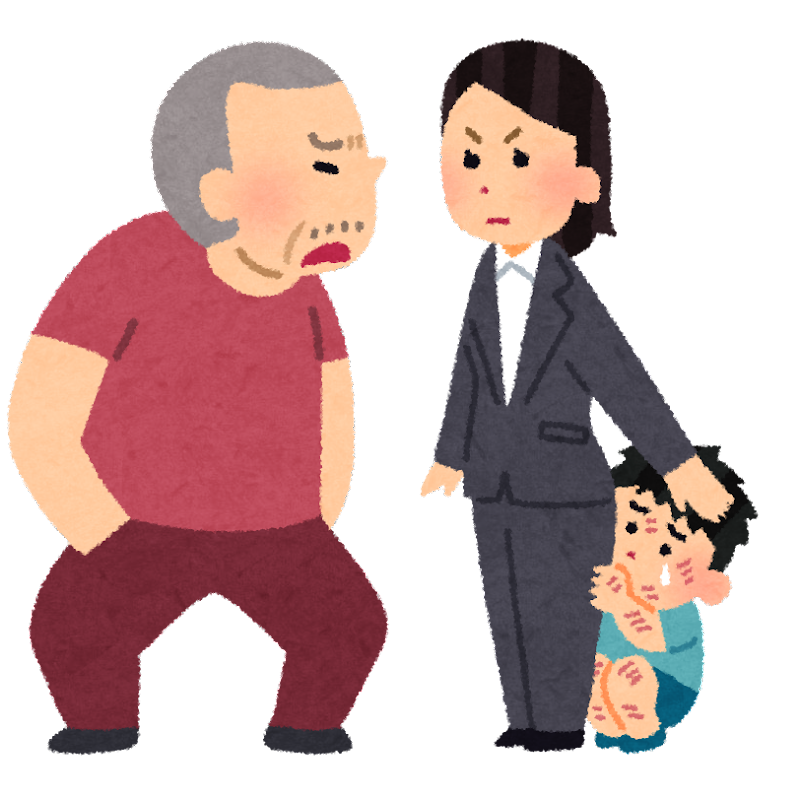
Aくん(5歳)は実親から暴力を受け、児童相談所に一時保護になりました。その後、児童養護施設に入所しました。実親に対する恐怖心もあり、面会は制限されています。実親はAくんを引き取るつもりでいます。施設ではAくんに対して職員さん(多くは保育士)が温かく接してくれていますが、一対一で相手してもらう時間が少なく、誰にも甘えることが出来ずにいました。

実親、施設、児童相談所が協議を行い、里親Bさんに委託が決まりました。Bさん夫婦は子宝には恵まれませんでしたが、子育てをしたい気持ちから里親に登録していました。そうして、Aくんと里親Bさんとの生活が始まりました。
養護施設ではなく、里親家庭での養育が勧められるのはどうして?

子どもたちの養護施設には、3歳未満の乳児院と、3歳以上の児童養護施設があります。幼い乳児や児童には、特定の大人との親密な関係が必要です。子どもは安心出来る基地を持つことで、初めて外の世界への興味を持って自我が芽生え成長することができます。そういった関係が持てないと、人を信じることが出来なくなったり、自分に自信を持てなくなったり、対人関係で問題が起こるリスクが高くなるといわれています。もちろん、実親とそう言った関係築くことがベストでしょうが、残念ながらそれが叶わない場合もあります。そういう子どもにとっては、実親の代わりに深い愛情を持って育ててくれる親代わりの里親が必要になります。
養護施設では沢山の子どもたちを養育しています。職員さんを長時間独占して抱っこしてもらったり、思い切りワガママを言ったりすることは出来ません。どこかで我慢したり、諦めたりすることも多いはずです。子どもらしい生活をさせてあげるためにも、家庭で養護してあげる必要があるのです。
どんな人が里親になれるの?

里親になるためには、研修を受ける必要があります。詳しくは自治体の児童相談所が設けている里親制度をご参考ください。座学と施設での実習が必要です。年間でスケジュールが決まっていることが多いため、約半年程度で研修は終了です。研修を受けることは誰にでも出来ます。
里親の欠格事由としては、
- 経済的に困窮していないこと
- 本人またはその同居人が、児童に関するの法律(売春、ポルノなど)の刑に処せられていないこと
- 児童虐待やその他児童の福祉に関して著しく不適当な行為がないこと
とされています。当たり前の条件だと思います。
簡単にいうと、子どもに対して愛情をしっかり持つことが出来る人(性的なものは除外)であれば、どんな人でも里親になれるということです。
特別な人じゃない、あなたでもなれる!

ここまで読んでみて、このように感じる方もいらっしゃるかも知れません。
- 「責任が重そう」
- 「子どもに対して、そこまでの情熱がもてるかな」
その通りです。子どもを育てるということは責任も、情熱も必要です。しかし、どんな親だって初めから親としての意識が育っていた訳ではありません。子どもを育てながら親になっていくのです。それは里親も同様です。だから、まずは一歩踏み出してみませんか?里親の場合は、委託前にマッチングと言って里子と何回か顔を合わせてお互いの相性を見てから、委託が決まります。合う、合わないは言葉で説明できるものではありません。自分自身の感覚に正直に向き合うことが、里子も里親も、互いを良い方向へ導いてくれると思います。不安や迷いがあって当然です。里親支援専門相談員さん、児童相談所の職員さん、施設の職員さん等と話し合いながら進めていくことが大切です。
この記事によって、あなたの力が必要としている子どもたちに届くことを願います。
くらしま心の相談室では、里親のことから、子育て、自身のお悩みなど幅広く対応しております。お気軽にお問い合わせください。
公式LINEにて無料カウンセリングを実施中!