このブログでは、里親にも登録している臨床心理士が子どもの心について分かりやすくお伝えしています。
里親には4つの種類があって、どんな制度なのかについては【里親を知ろう①】で説明しました。
【里親を知ろう①】の記事はこちら↓↓


とある養育里親家庭を事例[2歳の子供(仮名:Aちゃん)]に実際どのような生活をしているのか?具体的に聞いてみたいと思います。[個人が特定されないように部分的に改訂しています]。

Aちゃんを預かるまでの実際の様子をお伝えします。
里子を迎える前にすること①


児童相談所から連絡あり、里子を迎えると決めてから、実際に子どもが家に来るまでには、ケースにも寄りますが、若干の準備期間があります。我が家の場合は2週間の準備期間でした。
その間に準備したモノは以下の通りです。
・チャイルドシート…子供を迎えに行く時にまず必要です。児相で貸し出しもしてくれますが、今後必要になるため、早めに購入しておきます。
・寝具…衣服は家からいくつか持ってきますが、寝具は無いことが多いです。子供用の布団や、パジャマを買い揃えます。
・食器…子供用のものを買い揃えます。子どもでも、”自分のもの”があることはとても大切です。食事は生活の要なので、セットで準備します。
・おもちゃ…「こんなの後でも良いでしょ?」と思われるかもしれませんが、子どもの生活環境が大きく変わる時です。何か少しでも楽しめるものを準備しておくと良いでしょう。
衣食住を整えること、これを意識できればOKです。
準備物を揃えつつ、児童相談所で、数回で面会を行います。子どもなので一緒に遊ぶ、同じ空間に居るという時間を過ごしました。里親と里子が合うか否かを見極めるマッチングと言われる過程がありますが、緊急性のある場合は数回会って、そのまま委託になるケースもあります。
里子を迎える前にすること②


私も夫も、里親になったことをそれぞれの職場に説明しました。それは子どもが急病になった際、欠勤、早退しないといけない可能性が高いからです。どのポジションまで説明するかは、夫、私それぞれに判断しました。私の場合は、全ての人に言う必要は無いかなと思い、管理職や勤務を担当している部署の方に説明をしておきました。
発熱やコロナで保育園が閉鎖になったりしたことがあり、事前説明しておいたお陰でスムーズに休みを取ることができました。
子どもはまだ免疫力が低く、色んな病気にかかりやすいです。色んな病気にかかることで、強くなっていくものなので、”周囲に里親になり、子どもを預かることになったことを伝える”ことは必要だと感じます。
迎え入れ初日


この日のことは今でも忘れられません。
まず児相に子供を迎えに行きました。平日だったこともあり、私1人で向かうことになり、それ自体も不安でした。一緒に遊ぶことには慣れてきたようで、Aちゃんはニコニコして遊んでくれました。しかし、いざ私の車で帰ろうと誘うと、大泣きして大暴れ。児相の職員さんと、おもちゃやお菓子でご機嫌をとってみたり、色々と手を尽くしましたが、どんどん時間が過ぎ、日が落ちて暗くなってきました。職員さんと一緒になって、少々強引にチャイルドシートに乗せ、車で自宅に向かいました。最初は泣いていたものの、少し疲れ、泣き止んでくれたAちゃん。そして、我が家に到着しました。夫は仕事で帰りが遅かったため、夫の母にも来てもらいました。 うちに着く頃にはすっかり泣き止んでいたAちゃん。でも、不安そうな顔はしていました。うちへ入ると、まず待っていたのは、うちのワンコ。ちょっとビックリしたAちゃんでしたが、泣くこともなく。ワンコは可愛いお客さんに大興奮でした。そしてAちゃんは、おもちゃが並んだ部屋へ入って行きました。新品の箱を見つけて、「あーー!」と指差すAちゃん[注:この時はまだ上手にお喋りが出来ませんでした。]一緒に開けてみると、どんどん箱の中から出していき、興味津々の様子でした。この時、「買っておいて良かった〜」と本当に思いました。子どもは”新しいもの”に目がありません。しかも、自分に用意された物であれば尚のことです。 そうこうしていると、夫の母、夫も帰ってきて、急に賑やかになりました。私は食事の支度をし、みんなで一緒になって遊んでいました。 Aちゃんはとてもお利口さんで、食事もよく食べ、その後にはお風呂にも入り、夜もすんなり寝てくれました。かなり疲れていたのもあったと思います。 しかし、夜泣きはありました。2時間おきに起きて、抱っこしてウロウロと歩きます。しばらくすると寝るので、下ろします。それを繰り返し…朝を迎えました。この夜泣きが、私の体力的には一番大変でした。夜泣きは3日間続きましたが、4日目からは少しずつ睡眠時間が伸びました。里子にある”お試し行動”だったのかもしれません[*お試し行動:自分を受け入れてくれるかどうか里親を試す行為]。現在では、2〜3ヶ月に1回、体調不良の時には夜泣きでグズグズすることがありますが、ゆっくり眠れている日が多いです。
お試し行動についてはこちらの記事で詳しく書いています。

生活の流れと初めての週末

里子のAちゃんは平日は保育園を利用しています。入園や、保育の条件に関しては各自治体によって異なりますが、保育園利用料は社会的養護として負担してもらえる自治体が多いようです。

今までと同じ保育園のため、先生もお友達も一緒です。保育園は、我が家からは少し距離がありましたが、生活環境を一度に全て変えてしまうのはストレスが大きいと考え、同じ園に通園することにしました。平日は私も夫も仕事なので、保育園に預け、夕方に迎えに行き、ご飯食べて、お風呂に入って、寝るという流れです。
そして週末は初めて一緒に1日過ごすことになりました。
大人は「休みだから、ゆっくり寝ていよう」なんて思いますが、子どもはそうはいきません。
Aちゃんの場合もは平日と同じ、朝6時に起きます。そこから朝ごはんや朝の準備は平日と同じですが、全て整っても8時頃。おもちゃで遊んでみたり、外遊びをしてみたり、お買い物に行ってみたり…今ではいくつかバリエーションが思いつきますが、子育てをしたことが無い私たちは「何しよう?どこ行こう?」と迷うばかりでした。
また、Aちゃんはまだまだ甘えたがりで、抱っこを求めるので、遊ぶ以外は長時間抱っこすることになり、身体的にも負担が大きかったのも覚えています。親戚からもらった抱っこ紐も大活躍でした。
そして、初めての週末はご近所さんへご挨拶周りもしました。子どもがいない家に、急に子どもがやってきたら、ビックリしますよね?普段からご近所付き合いなく、子どもの有無すら知らない状況なら問題はないと思います。しかし、我が家は地方で近所付き合いも多少はあるので、先に周りに知らせておきたいと、主人と2人で決めていました。
我が家の場合は、お隣さんと、知り合いの家で合計6軒をAちゃんとお菓子を持ってご挨拶に行きました。初めはどんなリアクションなのか分からずドキドキしました。
うちの場合はこんな風に説明しました。
「この度、里親になって子供を預かることになりました。まだ小さいので騒音もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。」
どんなリアクションだったかというと…
有り難いことに、どこの御宅でも本当に受け入れていただけました。上の2つは、自分の中では抜け落ちていた事だったので、「あ、そうか」と驚きもありました。我が家としては、社会貢献というよりも「子供を育ててみたい」という気持ちが強い中で決断したことでした。
そして下の2つのように、「子どもは宝」と言いますが、居るだけで、みんな自然と笑顔になって話しかけてくれました。子どもの存在は本当に偉大だと感じさせられます。
まとめ
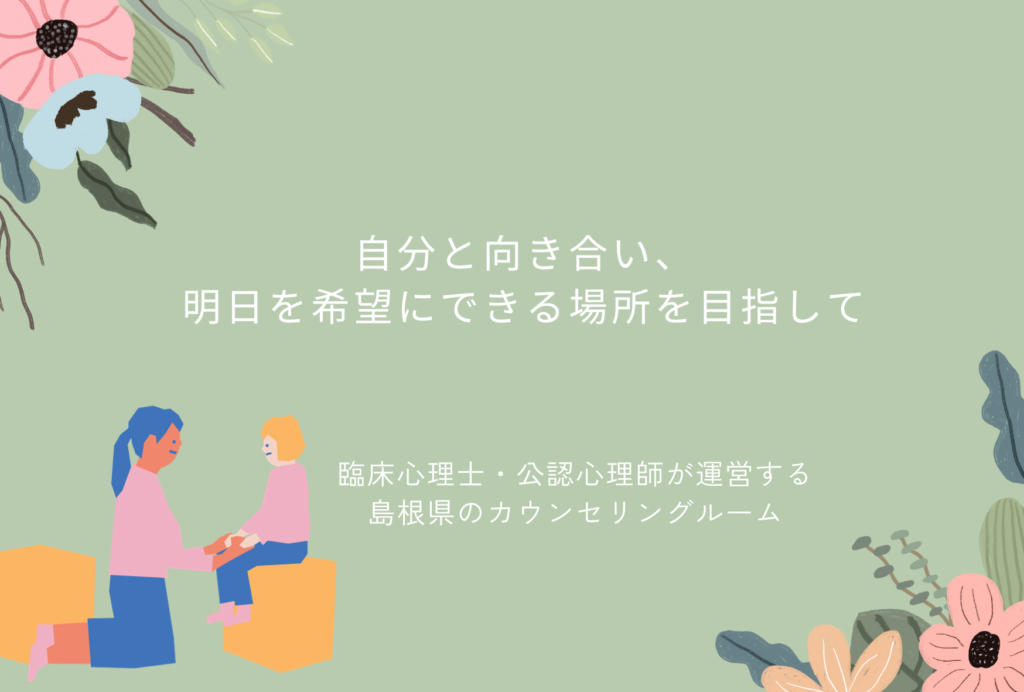
今回は里子を迎えた時の実際の様子をお伝えしました。まだやったことがない方も、これから里親になろうとしている方も、参考になると嬉しく思います。
くらしま心の相談室では、里親のことから、子育て、自身のお悩みなど幅広く対応しております。お気軽にお問い合わせください。
公式LINEにて無料カウンセリングを実施中!
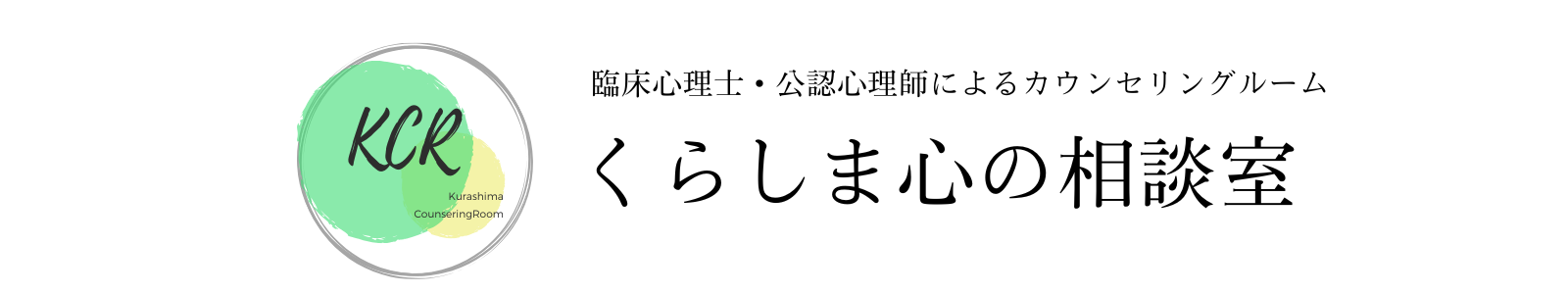



・「それは素晴らしいことですね」
・「社会に貢献した活動ですね」
・「とても可愛いお子さんですね」
・「仲良くしてね」